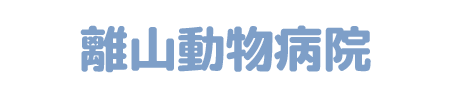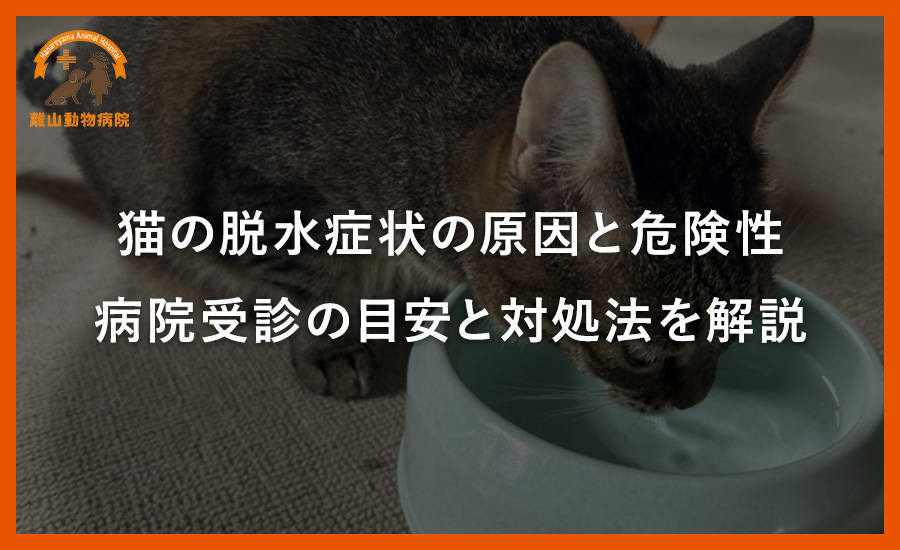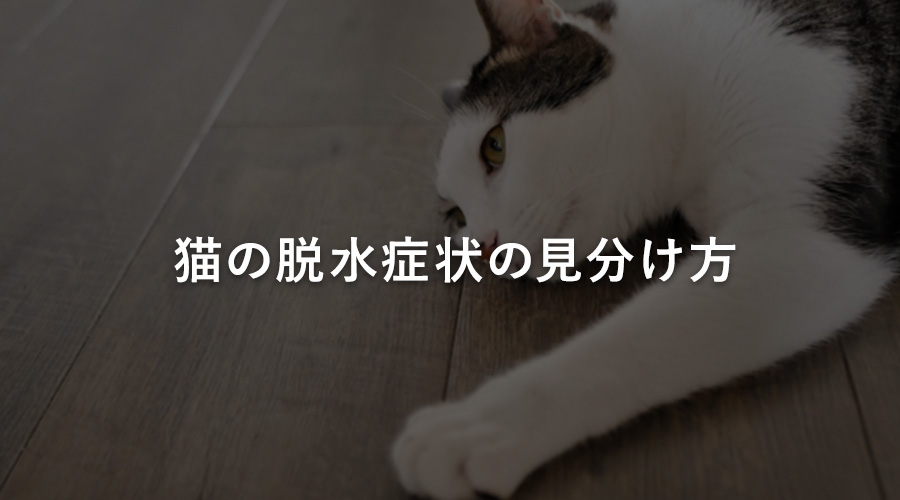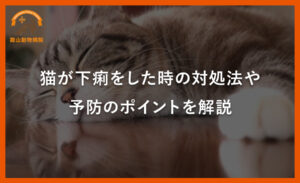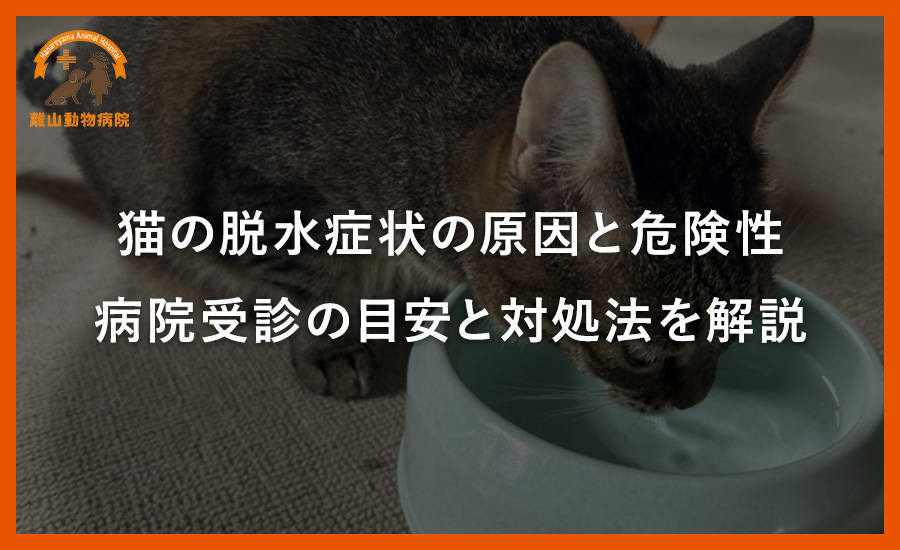
近年、猛暑の折、熱中症で脱水症状を起こす方が多くいます。
人間と同じように、猫も脱水症状を起こすことがあります。
ここでは、猫の脱水症状について、その原因と危険性についてご紹介いたします。
猫の脱水症状の原因とは?
猫の脱水症状については、体内の水分不足が原因と考えられ、そのなかでも、おもに3つの原因が考えられます。
それぞれについて見ていきましょう。
熱中症
高温のところに長時間いることにより、熱中症を起こし脱水症状になることがあります。
- 暑い日に車に長時間放置する
- クーラーをかけていない部屋で留守番させる
- こたつやホットカーペットの上に長時間いる
このような環境で熱中症を起こし、脱水症状を引き起こすことがあります。
下痢・嘔吐
下痢や嘔吐をしている場合、体内の水分と電解質を体外に排出してしまいます。
そのため、脱水症状を起こしやすくなります。
水分補給、点滴や経口補水液による電解質の補給が必要になります。
病気
脱水症状になりやすい病気としては以下のものが挙げられます。
- 糖尿病(血糖値の上昇にともない、細胞内の水分が細胞外に移動するため、細胞内脱水になることと、尿量が増えることにより脱水症状になりやすくなります。)
- 腎臓病(急性腎不全、慢性腎臓病になると脱水症状を起こすことがあります。)
- 肝疾患(下痢、嘔吐などの症状をともなうこともあるため、脱水症状を起こしやすくなります。)
- 膵炎(下痢、嘔吐などの症状をともなうこともあるため、脱水症状を起こしやすくなります。)
猫の脱水症状の見分け方
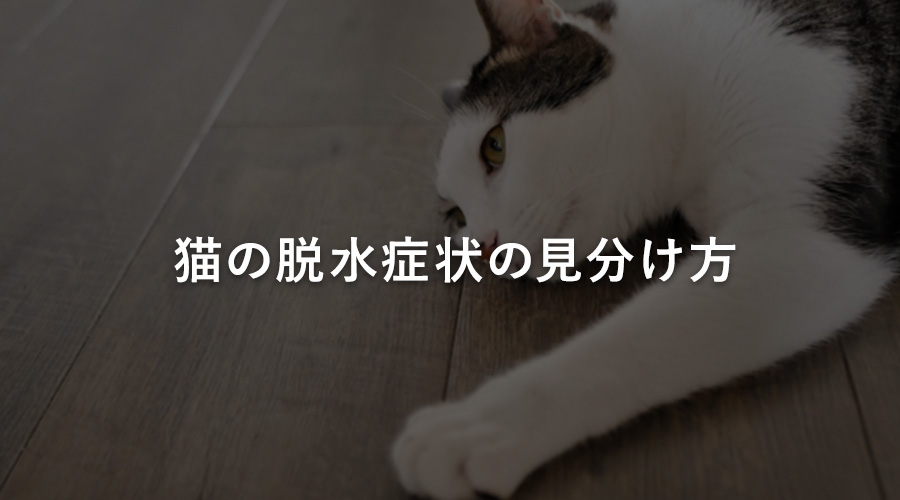
それでは、「愛猫が脱水症状かも?」と思ったときに、実際に猫が脱水症状がどうかを見分ける方法についてご紹介いたします。
見ただけで分かるサイン
猫の脱水症状を調べる方法にテントテストと呼ばれるものがあります。
これは、皮膚の弾力性の低下の度合いを見るものです。
猫の首から背中あたりの皮膚をつまんで持ち上げてみましょう。
手を離したときに、元に戻るのに時間がかかる場合は、脱水症状を起こしている可能性があります。
このほか、
- 結膜や口腔粘膜が乾燥している、粘膜が脂っぽく感じられない場合
- 目がくぼんでいる、瞳孔が変化している
- 元気がなく、ぐったりしている
- 食欲がない・嘔吐・下痢を繰り返している
このような兆候が見られたら、脱水症状を起こしている可能性があります。
動物病院を受診しましょう。
行動・生理的サイン
脱水症状になると、行動や生理現象に現れます。
次のような兆候が見られたら、脱水症状の可能性があります。
- 心拍数が増加し、呼吸が速くなり、体温が上がる
- 尿があまり出なくなり回数も減少する
- 水を飲む量が極端に少な口なる、もしくは全く水を飲まなくなる
脱水症状を起こしたときの対処法と病院へ連れて行く目安
ここからは、愛猫が脱水症状を起こしたときにどうすれば良いのか対処法と、病院に連れて行く目安についてみていきます。
家庭での対処法
まずは愛猫に水分を取らせましょう。
このときに注意する点は、「少量ずつ、頻繁に」です。
猫に自分で飲むようにうながすようにしましょう。
このとき、動物用の経口補水液などを与えことをおすすめします。
水をなかなか飲まない場合には、ウエットフードを利用したり、フードをお湯でふやかして水分摂取させるようにしましょう。
嘔吐がある場合は無理に飲ませず、嘔吐が治まってから徐々に再開するようにしましょう。
病院へ連れて行く目安
嘔吐や下痢が続いている場合、嘔吐物に血液が混じっている場合はすぐに動物病院を受診しましょう。
24時間以上、水分摂取が補えず、元気が回復しない、または尿がほとんど出ない場合はすぐ動物病院へ連れていきましょう。
また次のような場合には、様子を見ずにすぐに動物病院を受診しましょう。
- 体重が大幅に減少している
- 元気が全くない
- 立てない
- 呼吸が乱れている
- テントテストで脱水症状の可能性が濃厚
- 粘膜の乾燥がひどい
- 子猫
- シニア猫
- 持病のある猫
- 体温が不安定
- ショックサインが見られる(四肢が冷たい、意識混濁、意識レベルの低下)
脱水症状を防ぐ方法
愛猫の脱水症状を防ぐには、給水環境の整備が重要なポイントになります。
新鮮な水を常に用意し、複数箇所に置いておき、愛猫がいつでも水を飲める環境をつくりましょう。
猫が飲みやすい温度(常温ぐらい)にしてあげると良いでしょう。
また、ウェットフードの割合を増やしたり、水分量の多い缶詰を取り入れることも大変効果があります。
また環境整備と生活習慣の改善も行ないましょう。
暑い季節には室温を適正に保ち、直射日光を避けられる場所を用意してあげましょう。
飼い主さんが、日々水分補給をうながすようにする時間をつくり、猫が水を飲んでいる際、痛そうにしていないかなどを定期的にチェックするようにすると良いでしょう。
体重の変化に気を配ることも重要です。
急激な体重減少は脱水だけでなく他の病気のサインにもなり得ます。
日頃から気をつけてあげると病気にも気づくことができ、一石二鳥です。
まとめ
脱水症状は原因はさまざまです。
たとえ軽度でも、進行すると体へ大きな影響を及ぼす可能性があります。
特に子猫とシニア猫は脱水に対する耐性が低いため、早期の判断と適切な治療が重要です。
飲水の減少、嘔吐・下痢、元気の低下などのサインがあれば、速やかに獣医師へ相談するようにしましょう。
日頃からの飼い主さんによる脱水予防対策も重要です。
この記事の監修者
獣医師 出家 淳
離山動物病院 院長
川西市周辺地域の動物病院として予防・治療にあたるだけではなく、ミネルバ動物病院と連携をとりながら高度医療が必要な患者様への医療提供も実施していきたいと思います。
動物のため、飼い主様のために何がベストなのかを常に考えながら予防や治療にあたって参ります。