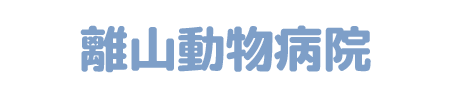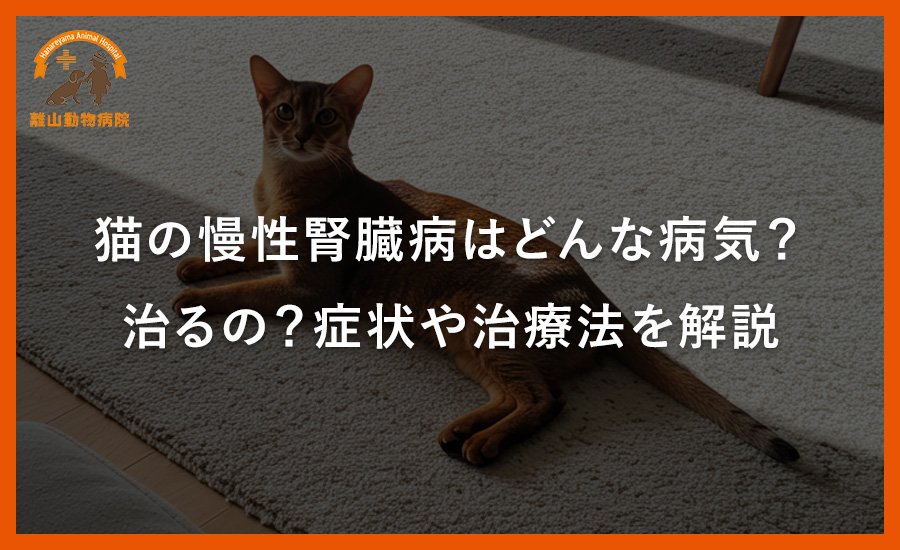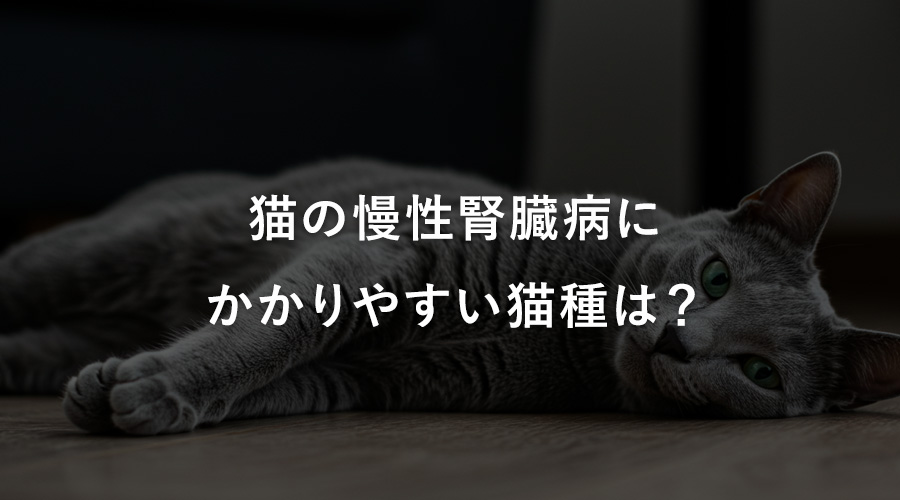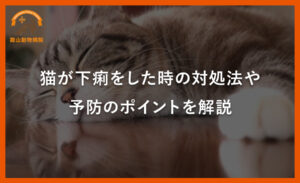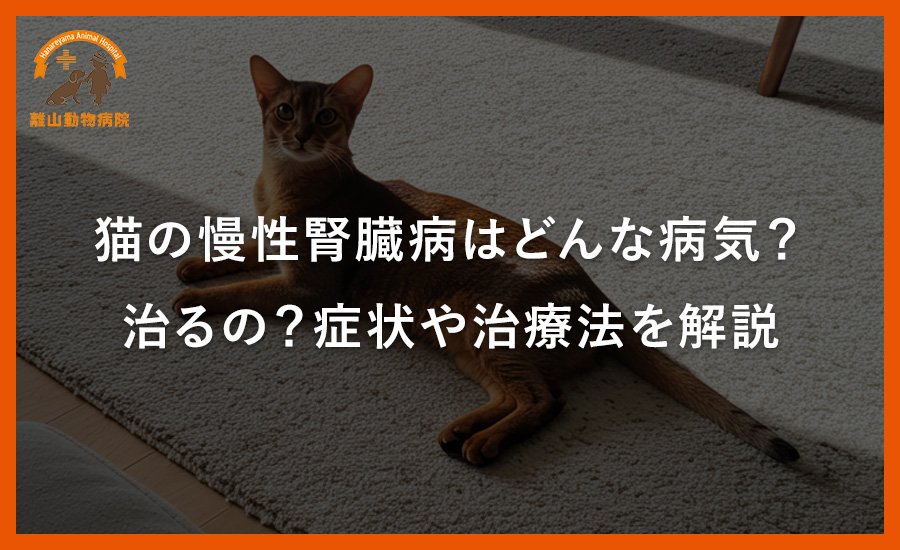
猫の慢性腎臓病について、愛猫家の皆さんはどれだけご存じでしょうか?
ここでは、高齢になると品種を問わず、なり得る可能性がある猫の慢性腎臓病について、詳しく解説してまいります。
腎臓の役割について
まずは、腎臓の役割についてご説明いたします。
腎臓には、3つの機能があります。
ろ過、再吸収、内分泌です。
具体的には、
老廃物を身体から排出し、血圧を調整する機能、赤血球の分化と増殖を促進し、身体の水分量やイオンのバランスを保つ働きを担っています。
慢性腎臓病とはどんな病気?
慢性腎臓病は、3ヶ月以上持続している片側または両方の腎臓の構造的・機能的異常のことを指します。
つまり、腎臓がダメージを受け続けた結果、回復し得ない状態で腎臓機能が低下している状態であるということになります。
- 本来は尿と一緒に排泄されるべき物質が血液中に残ることによって尿毒症を発症する
- 血圧調整がうまくできなくなることで高血圧になる
- 赤血球の成熟・増殖が不十分になることにより貧血を引き起こす
- 体内水分量を維持できずに脱水症状になる
このような症状を引き起こすのが慢性腎臓病です。
慢性腎臓病は、ゆっくりと進行します。
そのため、なかなか気づきにくい病気でもあります。
初期段階では、ほとんど異常は見られず元気も食欲もあるため、慢性腎臓病を疑うことは少ないでしょう。
慢性腎臓病の診断基準には、次のような記載があります。
「脱水症状がなく体調が安定している状態で、2回以上の血液検査によって診断する」
元気があるから、食欲もあるからといって慢性腎臓病でない可能性はゼロではありません。
少しでも疑いがあるようであれば、早めに治療をする必要があります。
なぜなら、一度失われた腎臓の機能は、二度と元には戻らないからです。
猫の慢性腎臓病の4つのステージ
猫の慢性腎臓病には、4つのステージがあります。
ステージ1:一見異常がみられない
一見異常は見当たりません。
血液検査においても異常は見当たりませんが、尿検査で異常が見られる、腎臓の形状異常が見られることがあります。
このときすでに、腎臓の機能は通常の3分の1に低下している状態です。
ステージ2:多飲多尿
ここに来て多飲多尿が見られるようになります。
腎機能が4分の1にまで低下しているので、薄い尿を大量にするようになります。
ほとんどの子が、食欲もあり元気もあるので、気をつけて見ていないと分からない飼い主さんがほとんどでしょう。
ステージ3:尿毒症を発症し始める
この頃になると、老廃物や有害物質の排泄ができなくなっており、尿毒症を発症し始めます。
血液中に尿毒素が混入するため、口腔内や胃のなかが荒れ、口内炎や胃炎になりやすくなります。
徐々に食欲が落ち、嘔吐も見られることから、飼い主さんも気づき始めます。
この頃になると腎臓の機能は10%ほどに低下しています。
ステージ4:尿毒症が進む
尿毒症が進んでいます。
残存腎機能は5%以下まで低下しています。
治療に専念しないと、命の危険があります。
猫の慢性腎臓病にかかりやすい猫種は?
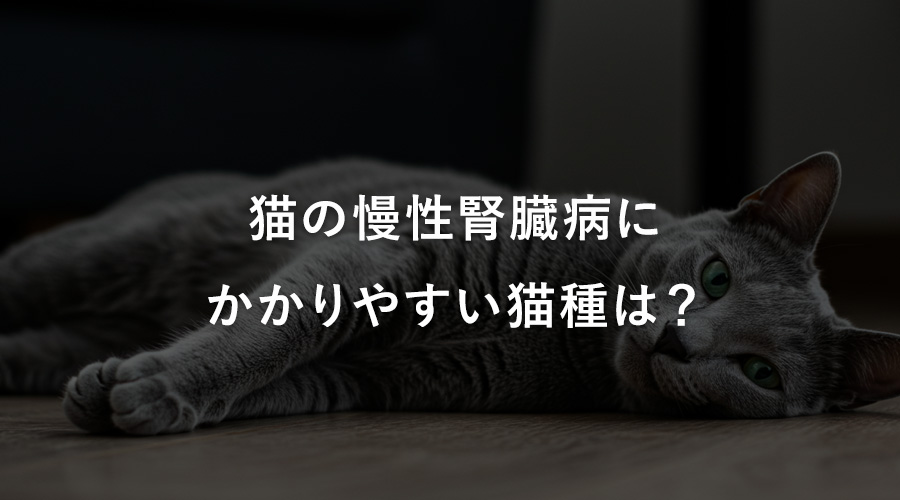
猫の慢性腎臓病にかかりやすい猫種としては、メインクーン、アビシニアン、シャム、ロシアンブルー、バーミーズが挙げられます。
これらの猫種は、遺伝的な要因が関係しているとも考えられているようです。
また一般的に、猫種に関係なく高齢猫の場合は、慢性腎臓病になりやすいとも言われています。
猫の慢性腎臓病の症状とは?
猫の慢性腎臓病の症状について見てみましょう。
多飲多尿
猫は1日におよそ50ml/kg、尿は50ml/kg以下が目安とされています。
これより尿の量が増えたり、尿の色が薄くなった、尿の匂いがしないなどといった尿に異常がみられたら、早めに動物病院を受診しましょう。
体重の減少
慢性腎臓病になると、数週間〜数ヶ月で体重が減少します。
体重減少は、一見しては分からないことが多いので、日頃から定期的に体重測定をしたり、定期検診をすることをおすすめします。
嘔吐
吐き気、嘔吐、食欲不振、胃炎、消化管潰瘍、下痢、大腸炎など、消化器症状も慢性腎臓病のよく見る症状です。
これらは、尿毒症を発症したことにより起こる症状です。
初期段階では、尿毒症を断定できないことも多く、また他の疾患でもみられる症状であるため、気になる症状があれば、まずは動物病院を受診することをおすすめします。
慢性腎臓病の原因とは?
慢性腎臓病の原因はさまざまです。
- 感染症・外傷・薬物などによる中毒
- 心筋症やショックなどによる腎血流量の低下
- 免疫疾患などによる腎炎
- 結晶や結石などによる尿路の閉塞
腎臓病の指標のひとつとしてCre値(クレアチニンの値)があります。
この値が上昇を見せるのは、腎機能の75%以上が失われてからです。
そのため、早期発見が難しいとされていましたが、近年、新たにSDMAという指標が使用されるようになりました。
SDMAであれば、腎機能が25%失われた状態でも上昇するため、早期発見ができるようになりました。
慢性腎臓病に大切なのは、早期発見、早期治療です。
猫の慢性腎臓病の治療法とは?
猫の慢性腎臓病の治療法として、食事療法が挙げられます。
低タンパク食に加え、PO4(リン酸塩)、Na(ナトリウム)の制限、ビタミンB群の添加、カロリー密度の上昇、可溶性繊維やω-3脂肪酸・抗酸化物質の添加などに加え、猫ではK(カリウム)が添加されていることも多くみられます。
慢性腎臓病を根治する薬は残念ながらありません。
投薬など内科的治療は、支持療法や緩和療法として用いられます。
腎臓への負担を最小限にして慢性腎臓病の進行をできる限り遅らせることを目的とした治療になります。
このほか、近年では再生医療という選択肢もあります。
健康な猫から脂肪組織を採取し、体外で細胞を培養します。
培養した細胞を慢性腎臓病の猫に投与するという治療法です。
これは、身体が本来持っている修復機能や自己治癒力を利用して病気を治すというものです。
現在のところはまだ臨床研究段階ですが、動物病院に相談してみるのも良いでしょう。
まとめ
慢性腎臓病に予防法はありません。
慢性腎臓病は初期症状においてはほぼ変化がないため、発見が遅くなることが多いのが現状です。
しかしながら、定期的に検診を受けていれば、早期発見することも可能です。
慢性腎臓病と診断されたら、生涯病気と付き合っていかなければなりません。
愛猫に長く健康でいてもらうためには、飼い主さんは愛猫と寄り添う姿勢が必要になります。
この記事の監修者
獣医師 出家 淳
離山動物病院 院長
川西市周辺地域の動物病院として予防・治療にあたるだけではなく、ミネルバ動物病院と連携をとりながら高度医療が必要な患者様への医療提供も実施していきたいと思います。
動物のため、飼い主様のために何がベストなのかを常に考えながら予防や治療にあたって参ります。